日本人の配偶者の帰化 | 配偶者ビザからの帰化申請を解説

日本人と結婚した外国人の多くは、日本での生活を長期にわたって続けることになります。日本社会に根ざした暮らしの中で、「この先もずっと日本で生活していきたい」「いずれは日本国籍を取得したい」と考える方も少なくありません。
そうした方にとって選択肢のひとつとなるのが「帰化申請」です。実は、日本人の配偶者である外国人は、日本との結びつきが強いとみなされるため、一般の外国人よりも帰化の条件が一部緩和されています。
本記事では、配偶者ビザで日本に滞在している外国人が帰化申請を行う際の要件や注意点について詳しく解説していきます。
目次
配偶者ビザからの帰化申請
配偶者ビザで日本に滞在している外国人が、より日本で安定的に生活していくためには、どのような方法があるのでしょうか。
帰化と永住の違い
配偶者ビザで日本に滞在し、「この先もずっと日本で生活したい」と考えたとき、多くの方が選択肢として検討するのが「帰化」または「永住」です。この2つはどちらも日本に長期的に住み続けることができる在留資格ですが、最も大きな違いは「国籍」にあります。
「帰化」は日本国籍を取得することであり、これにより戸籍が作成され、日本のパスポートを持ち、日本人として生活していくことになります。一方、「永住」は在留資格が「永住者」となるだけであり、国籍は外国籍のままです。
以下に、帰化と永住の主な違いをまとめました。
| 帰化 | 永住 | |
|---|---|---|
| 国籍 | 日本国籍 | 外国籍のまま |
| 戸籍 | あり | なし |
| パスポート | 日本 | 母国 |
| 選挙権 | あり | なし |
| 取消事由 | なし | あり |
帰化することのメリット
日本に帰化することで、日本国籍を取得し、日本人として生活することができるようになります。これは単なる在留資格の変更ではなく、法的にも社会的にも日本の一員となることが出来ます。日本人になることで、下記のようなメリットがあります。
■ 日本のパスポートを取得できる
日本に帰化すると、日本のパスポートが発行され、ビザなしで渡航できる国が大幅に増えます。世界的にも信頼性の高いパスポートのひとつであり、国際的な移動がしやすくなります。
■ 選挙権や公務員試験の受験資格を得られる
帰化すると国政・地方選挙で投票が可能になります。また、警察官や自衛官など、一部の職種は日本国籍が条件となっており、これらの公的な仕事にも応募できるようになります。
■ 在留資格の更新や取り消しの心配がなくなる
永住者や配偶者ビザと異なり、「在留資格」自体が不要になるため、更新手続きや失効、取り消しなどのリスクがなくなります。将来的に離婚や配偶者の死亡があっても、日本に住み続けることが可能です。
このように、帰化は日本社会により深く根ざした暮らしを望む方にとって、大きなメリットがあります。
日本人の配偶者が帰化するための条件
日本人の配偶者が帰化する場合、一般の外国人と比べ、条件の一部が緩和されます。このように、条件の一部が緩和される帰化を「簡易帰化」と呼びます。
日本人の配偶者が帰化する主な条件について、詳しく説明していきます。
住居条件
一般の外国人の場合、引き続き5年以上日本に住所を有している必要があります。日本人の配偶者の場合、住居条件が緩和され、下記2パターンで住居条件を満たします。
日本に引き続き3年以上住んでいる
日本に引き続き3年以上住んでいる外国人は、日本人と結婚した時点で帰化申請が認められています。例えば、留学ビザや就労ビザで3年間日本に住み続けている外国人は、日本人と結婚すると帰化申請が可能になります。
「結婚してから3年待たないと帰化申請ができない」ことはありません。日本に継続して3年以上住んでいる場合、結婚後すぐに帰化申請が出来ます。
結婚から3年以上経過している
日本人と結婚して3年以上が経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいれば帰化申請が認められます。例えば、海外赴任先で日本人と結婚し2年が経過した後、日本に戻って引き続き1年以上経過しているような場合、帰化申請が可能になります。
素行条件
日本での滞在期間における素行が審査されます。具体的には納税状況や年金、健康保健、交通違反・犯罪歴の有無などが審査の対象となります。
納税
帰化申請では、住民税の納税証明書を提出します。納期未到来のものは問題ありませんが、納期を過ぎている未納分は問題となります。申請前に完納しましょう。
会社経営者や確定申告をしてる方は、別途法人税や所得税の納税証明書を提出する必要があります。
年金・健康保険
年金や健康保険といった社会保険の支払い状況も審査の対象となります。未納がある場合は不許可となる可能性が高くなります。
会社員や公務員のように、厚生年金や健康保険に加入している方は給与から天引きされているケースが多いので問題はないかと思います。
一方、自営業やフリーランス、無職で国民年金・国民健康保険に加入している方は注意が必要です。未納がある場合、遡って支払を済ませてから申請をしましょう。
違反・犯罪
違反・犯罪歴も当然に審査の対象となります。懲役や罰金刑だけでなく、交通違反にも注意が必要です。
軽微な交通違反であれば、5年間に3~4回程度までなら、許容される目安とされています。軽微な交通違反でも、2年以内に3回あれば不許可になる可能性は高いです。ただし、罰金レベルの赤切符を切られた場合は、1回でも帰化が難しくなります。
生計条件
外国人配偶者本人だけでなく、日本人配偶者を含めた世帯の収入が審査されます。外国人本人が無職でも、日本人の配偶者に安定的・継続的な収入があれば問題ありません。
一般的に、一人暮らしで申請する場合、年収300万円程度が必要になります。扶養家族が一人増えるとごとに50~70万円低度求められる収入額が増えていきます。
日本語能力
近年、日本語能力の審査は厳しくなっています。単に会話ができるだけでは不十分で、読み書きもできることが重要です。
「求められる日本語能力」
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有していること
日常生活に支障のない程度の日本語能力とは、小学校3年生程度の日本語能力とされています。
まとめ
配偶者ビザで日本に滞在している外国人が、より安定した生活基盤を築くための選択肢のひとつが「帰化申請」です。帰化によって日本国籍を取得すれば、選挙権や公務就労の資格が得られるほか、在留資格の更新や取り消しの不安からも解放され、法的にも社会的にも日本人としての生活が可能になります。
配偶者ビザからの帰化申請では、住居年数などの条件が一部緩和される「簡易帰化」が適用されるため、一般の外国人よりもハードルは低くなります。ただし、納税・社会保険の履行状況や交通違反・犯罪歴、日本語能力など、審査のポイントは多岐にわたり、事前の準備と情報収集が重要です。
「自分は帰化の条件を満たしているだろうか?」「どのタイミングで申請すべきか?」と悩まれる方も多いかと思います。確実に帰化申請を進めるためには、制度を熟知した専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、配偶者ビザからの帰化申請に豊富な実績があり、個別の状況に応じたサポートを行っております。お気軽にご相談ください。
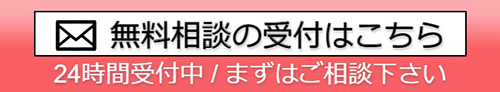
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
- 2025年5月26日コラム配偶者ビザで働ける?就労に関するメリットを解説
- 2025年5月16日配偶者ビザ配偶者ビザの更新で「1年」から「3年」にするには?ポイント解説
- 2025年5月14日配偶者ビザ日本人の配偶者ビザの申請 | 申請から許可までの完全ガイド
- 2025年5月12日配偶者ビザ配偶者ビザの申請方法|必要書類・申請場所・注意点を解説
まずはお気軽にご相談ください