配偶者ビザが不許可になる理由は?不許可の確率が高いケースと対応策

外国人の配偶者と日本で暮らすために必要な配偶者ビザですが、一見、結婚していれば問題なく取得できそうに思えるかもしれませんが、実際には不許可となるケースも少なくありません。
「なぜ不許可になるのか?」「どんなケースがリスクが高いのか?」「どうすれば許可されやすくなるのか?」本記事では、配偶者ビザの申請において不許可になる主な理由や、不許可の可能性が高いケース、そしてその対応策について、専門家の視点から詳しく解説します。
目次
配偶者ビザが不許可になる主な理由
「結婚しているのだから、配偶者ビザは当然に許可されるはず」と考える方もいるかもしれません。しかし、配偶者ビザが付与されるためには出入国在留管理局(入管)で審査を受ける必要があります。
入管では、「実態のある結婚かどうか」「日本での安定した生活が見込めるか」といった観点から、申請内容を厳しく審査しています。申請内容に疑義があると判断された場合、最悪不許可となることもあります。
ここでは、配偶者ビザが不許可となる代表的な理由を紹介します。
夫婦としての実態が確認できない
夫婦が同居していない、交際期間が極端に短い、言葉が通じないなどの事情がある場合、結婚の信ぴょう性が疑われやすくなります。「形式的な結婚」や「偽装結婚」ではないかと疑われるのです。
特に、出会い、交際、結婚までの経緯を十分に説明できない場合は、不許可となるリスクが高くなります。
経済的な基盤が不十分
日本人配偶者、または外国人配偶者に安定した収入や生活基盤がないと判断された場合、生活維持能力が疑われ、不許可となることがあります。
アルバイト収入しかない、無職、預貯金がないなどの場合には、生活の安定性を証明する補足資料が必要です。
素行や過去の在留歴に問題がある
過去にオーバーステイや違法就労(オーバーワーク)などがある場合、「素行不良」と判断されて審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
些細な違反でも、正直に説明し、反省の意を示すことが重要です。
不許可になったら
配偶者ビザの申請が不許可となったら、申請先の出入国在留管理局へ出向く必要があります。そこで、不許可通知と簡単な理由の説明が行われます。
この際、最も重要なのは「不許可の理由」を細かく確認することです。担当官はすべての理由を伝える義務がないため、代表的な事項のみが説明されることが一般的です。しかし、理由は複数ある場合もあるため、再申請に向けてすべての内容を把握しておくことが必要です。
なお、この場で抗議や再審査の要求をしても結果は変わらないため、不許可理由を正確に確認することに集中することが大切です。
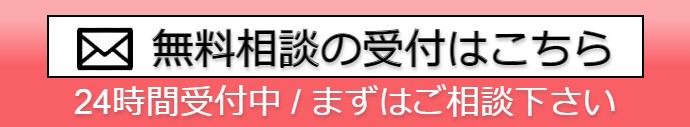
不許可の確率が高いケース
配偶者ビザの審査では、単に結婚しているという「形式」だけではなく、夫婦としての「婚姻・生活の実態」を重要視しています。過去には就労目的の偽装結婚の事例もあったため、入管側は疑わしいケースに対して非常に慎重に審査を行います。
ここでは、実務上とくに不許可リスクが高いとされる代表的なケースを紹介し、それぞれにどのような対応策が必要かを詳しく解説します。
交際期間が短い
出会ってから結婚に至るまでの交際期間があまりに短い場合、「ビザ目的で結婚したのではないか」という疑念を招きやすくなります。特に、スピード婚は入管から慎重に見られる傾向があります。
対策としては、出会いから現在までのやり取り(メッセージ履歴、電話・ビデオ通話記録)や、交際中の写真、来日時の渡航履歴、宿泊証明などを提出し、実際の交流の深さを示すことが重要です。また、交際開始から婚姻届提出に至るまでの経緯を丁寧に説明した理由書も併せて提出しましょう。
交際期間が短いカップルの配偶者ビザ申請は難しい?許可取得の対策を解説
夫婦の年齢差が大きい
夫婦間にあまり年齢差があると、一般的に見て不自然に感じられることがあり、「偽装結婚ではないか」といった懸念を抱かれがちです。特に、若い外国人と高齢の日本人との婚姻においては、入管も内容を慎重に確認します。
年齢差そのものが問題になるわけではありませんが、実際に恋愛関係として成立しているか、対等な関係であるかが問われます。出会いから結婚に至るまでの背景を丁寧に説明する文章や、日常のコミュニケーションの様子、家族ぐるみの交流などを証明する資料を積極的に提出しましょう。
夫婦の年齢差が大きい場合における配偶者ビザ不許可の理由と対策を解説
SNSや結婚紹介サイトで知り合った
インターネットや国際結婚紹介サービスで出会った場合、入管は過去の偽装結婚事例との関連を踏まえ、出会いの信憑性や実態を特に慎重に審査します。「実際に会った回数が少ない」「翻訳アプリを使わなければ会話ができない」といった場合は、結婚の実態が薄いと判断されることもあります。
信頼される申請にするには、初めて知り合った日から結婚に至るまでの経緯、実際に会った回数や期間、滞在中の写真や記録、交際中に相手の家族・友人と交流した事実など、出会いから現在までの関係の継続性と誠実性を証明できる資料を豊富に揃える必要があります。
SNSや出会い系サイト・アプリで知り合った外国人の配偶者ビザ申請の方法と注意点
離婚歴が多い
配偶者に複数回の離婚歴、ビザ申請歴があるがある場合、「過去にも同様のケースでビザ取得を目的に結婚したのではないか」と疑念を持たれる可能性が高まります。特に、直前の離婚から今回の結婚までの期間が短い場合は注意が必要です。
そのようなケースでは、過去の婚姻や離婚の経緯をきちんと説明した理由書を作成し、今回の結婚がどのようにして決まったかを丁寧に伝えることが大切です。
離婚歴があり再婚する場合の配偶者ビザ取得は難しい?問題点と許可取得のコツ
コミュニケーションが不足している
夫婦間で言語がまったく通じない、通訳がいないと意思疎通ができない場合、日常生活において支障があると判断され、「本当に共同生活をするのか」と疑われます。
こうした懸念を払拭するためには、お互いの言語でやり取りしているメッセージ、翻訳アプリを使いながらでも会話を続けている記録、日本語を勉強している様子を示すなど、具体的なエピソードなどを提出すると良いでしょう。
夫婦が別居している
夫婦が別居している場合、入管は「婚姻の実態がない」と判断し、高い確率で不許可となります。
別居がやむを得ない合理的な事情(転勤、ビザ未取得、介護など)がある場合、事情を詳細に説明し、頻繁な面会や連絡の履歴を示し、距離は離れているが夫婦生活が続いていることを証明する必要があります。
ただし、原則「夫婦同居」が配偶者ビザ取得の条件となります。
世帯の収入が少ない
世帯として収入が少ない場合、生活の安定性に疑念が持たれ、「日本で共に暮らしていくことが本当に可能か」という審査上の懸念が発生します。無職や低収入の状態で申請を行うと、不許可の確立が高くなります。
そのような場合は、今後の就労状況など生活改善計画、預貯金の残高証明、親族からの生活費援助を受けるなど、家計の見通しを明確に示すことが重要です。
なお、外国人配偶者が無職でも、日本人配偶者がしっかり働いている場合は問題にはなりません。
まとめ|配偶者ビザの不許可を避けるために大切なこと
配偶者ビザの申請では、単に「婚姻届を提出している」「法律上の夫婦である」というだけで許可が下りるわけではありません。入管は、その結婚に実態があるか、継続的な生活が見込めるか、そして日本で安定して暮らしていけるかといった視点で審査を行います。
特に、交際期間が短い、年齢差が大きい、SNSで出会った、収入が少ない、別居中といったケースでは、説明や証明が不足している場合には不許可になる可能性が高まります。
不許可を避けるためには、以下のポイントを意識した準備が重要です。
・結婚の実態と継続性を証明する資料をしっかり揃える(写真、通信履歴など)
・書類の整合性・正確性を確認する(一貫性のある記載)
・経済的基盤の安定性を示す(課税証明書、預貯金の明細など)
・やむを得ない事情がある場合は、丁寧に説明する(別居・年齢差など)
「結婚してるんだから大丈夫だろう」と思っていても、入管がどのように審査するかの視点が抜けていると、思わぬ理由で不許可になることがあります。
そのため、少しでも不安がある場合は、ビザ申請に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。事前にリスクを洗い出し、的確な対策を取ることで、不許可の可能性を大きく減らすことができます。
大切なご家族と日本で安心して暮らしていくために、万全の準備で申請に臨みましょう。
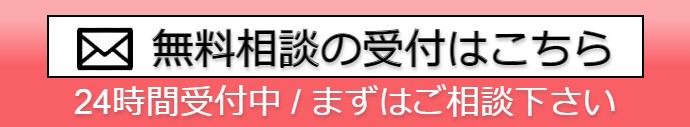
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
- 2025年5月26日コラム配偶者ビザで働ける?就労に関するメリットを解説
- 2025年5月16日配偶者ビザ配偶者ビザの更新で「1年」から「3年」にするには?ポイント解説
- 2025年5月14日配偶者ビザ日本人の配偶者ビザの申請 | 申請から許可までの完全ガイド
- 2025年5月12日配偶者ビザ配偶者ビザの申請方法|必要書類・申請場所・注意点を解説
まずはお気軽にご相談ください